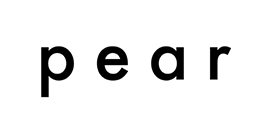こちらでは栗原の少し詳しい自己紹介をさせていただきたいと思います。
Contents
生い立ち
1977年愛知生まれです。大学進学まで愛知の郡部で過ごし、その後、東京と神奈川で12年ほど暮らしました。2009年から駐在や留学のため、上海(中国)、ロンドン(イギリス)、グジャラート(インド)で計6年間生活。2014年10月から再び東京で2020年から神奈川県三浦半島で暮らしています。
家族は、パートナー、子ども、インドからやってきた猫のヤンマーです。趣味はサッカー観戦。好きなものはデジタル製品とお笑いです。家電好きは小学生のときからはじまり、週の大半を電気屋訪問とカタログ収集に費やしていました。
リサーチ&データ分析と写真の異なる専門を持っており、実務で15年以上の経験があります。[リサーチ&データ分析:慶応義塾大学・修士、ドキュメンタリー写真:ロンドン芸術大学・修士]
キャリアのスタート
学生時代から、人の気持ちや社会の群集心理といった抽象的で見えないものを理解したいと考えていました。その関心はデータ分析やリサーチへ派生し、縁あってその興味をマーケティングの分野で追求することになりました。では、なぜ人の意識や行動に興味があったのか、ここではもう少しさかのぼってお話ししたいと思います。
学生時代 意識と行動の謎
日々の喜怒哀楽の中で、人の意識はどのような影響を受けて変化しているのだろう。二十歳の頃の私は、そのことに強い関心を持っていました。そんな時、立花隆氏の著書「精神と物質」や「臨死体験」と出会ったのです。意識という漠然とした存在を科学の視点で説明しようと、分子生物学や心理学、統計学など複数の分野を横断して書かれていました。この著者との出会いで、学びが有機的につながる体験をはじめて経験したのです。そして大学での専攻を決める段階になり、人の意識の謎に迫るためのアプローチとして、社会心理学や社会調査、データ分析に出会いました。
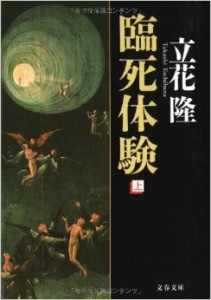

専門性を社会で活かす
学生時代には、学んだ専門性を実際に社会で活かすことができるのか懐疑的でした。経済学者の加藤寛先生はよく学生たちに対して「君たちには、先行きが全く見えない暗い今の日本を、明るく照らすミネルバの梟となって、人々を導くような社会人として活躍してほしい」と、仰っていました。(ヘーゲルの逸話を独自に解釈された話)
熱っぽく語る先生のその言葉を聞いた時、自分はリサーチやデータ分析を使い、人々や社会を明るく元気にする一助になりたいと考えるようになったのです。大学と大学院では、医療福祉分野の患者やサービス利用者の意識や行動に問題意識を持ち研究に取り組みました。(修士論文は「藤沢市における医療介護サービス利用の決定要因データ分析」)
ソニー時代 経験・勘・度胸と科学の融合
2003年にソニー株式会社に入社しました。当時のソニーはAIBOやQURIOというロボットを開発しており、イベントでそれらのロボットが直立歩行しながらダンスするのを見て、明るい未来を創るのに貢献できる会社だと共感したのです。
入社後の仕事は、リサーチやデータ分析の仕事を社内で推進する仕事です。しかし、専門知識はあっても、それをいつどのようなタイミングで活用すると会社の利益に結びつくのか試行錯誤が続きました。入社したての私は、実践経験に乏しくただ専門用語や分析ツールをふりまわすだけの頭でっかちだったのです。

会社では、営業、マーケティング、宣伝、商品企画、エンジニア、デザイナーと実にさまざまなメンバーと一緒に仕事をします。「その分析すると儲かるのか?」、「先が見えるのか」という問いに答えていく日々でした。
働き始めて3年ほど経ち、リサーチやデータ分析が社内で重要視されるようになったとき、もっとも大切だと気がついたことは、経験・勘・度胸(KKDと呼んでいました)を活かして更に科学的な視点を加えることです。
どれだけ科学的に優れたリサーチや分析をしようとも、このKKDが欠如していれば、深い気づきも得られないでしょうし、有効なアクションをとることも難しいことを知ったからです。
優れたマーケターは、自分の担当商品に関わるデータ(売上、マーケットシェア、競合商品、価格、顧客アンケート、クレーム、問い合わせ、店頭観察、社会トレンドなど)を日々大量に入手し考えています。そして、彼らは常に具体的な仮説を持っているのです。たとえば、商品の売上が見込みを下回った場合、なぜ売れないのかを漠然と問うのではなく、商品のセールスポイントの優先順位が間違っていたからである、といったより具体的で改善判断をすぐできるように仮説を持っています。
この経験に裏打ちされた勘、暗黙知を科学的な手法で検証し解釈することで、より成功の確率の高い意思決定が可能になるのです。そんなマーケッターとの仕事から勘と科学的な視点を併せ持ち、勇気を持って意思決定しやり遂げる力こそマーケティングであると学びました。
上海、はじめての長期海外生活
2009年上海へ転勤する機会に恵まれました。巨大な中国市場を対象に、マーケティングチームとともに仮説を考えたり、検証したり、よりよくセールスが伸びるようにしていくために活動を推進するのがミッションです。全国の都市に出張して、町や店舗を回り、計画がしっかり実行されているのかを見て、必要があれば改善することも大切な仕事のひとつでした。都市間の経済状況は大きく異なり、まずそこを実際に訪れることで得られる気づきが多くありました。

また私生活でも、はじめての長期の外国暮らしは、驚きの連続でした。当時、上海の町は万博に備えて激しい建築ラッシュで、地下鉄が10路線近く開通し、大きな駅の周辺には、ルイ・ヴィトン、BMW、無印良品、ユニクロとグローバルブランドが軒を連ね、来る前に抱いていた印象とは大きく違っていたことを憶えています。





表現力を鍛えたい
駐在生活を2年半続けて中国の人々の趣向や行動習慣に触れ続けるうちに、異なる文化や市場の状況をどのようにしたらリアルに心に響くように届けられるか、既存の定量・定性調査に足りない部分への問題意識を持ち始めました。インサイトという言葉がありますが(私はそれを心の深いところで納得感のある気づきと理解しています)、そういった気づきを誘発したり、伝えるためにできることを模索していたのです。

その頃から可能性を感じていたのが、ビジュアルの活用と応用です。特に、 リサーチを下敷きにした写真を、リサーチやアイデア創造に向けて活用できないかというアイデアがありました。
本社の商品企画部やマーケティング担当者とデータを交えた議論を本社で行ったり、また現地でフィールド調査を一緒にする機会が度々ありました。統計データは、事実をまとめて判断しやすくはしてくれます。
たとえば、色やデザインの好みを測定すれば、その人気投票の結果はわかります。しかし、選ばれた意味まで理解するには、数値だけでは難しく、ファッションなどライフスタイルのトレンドを実際に見て、全体を通して解釈していく必要があります。
そのような場合、データを見るとともに、写真を使ってインスピレーションを得ることは有効です。ただ闇雲に写真を集めるというより、いつどこで誰が、どんな気分でのように、リサーチのフレームワークを使ったり、内容を読み解いたり、意見を交換するメディアとして活用できるはずだと考えたのです。
現地でのフィールド調査にしても、限られた時間の中で見られるものは限られますから、事前にビジュアルイメージやデータを元に、深く見つめるべきポイントを仮説として持っておくことは、限られた時間を有効に使ってインサイトを得ることができます。
「写真を使ったコミュニケーションの方法と技術を本格的に学んで、リサーチに活用したい」、その思いが募った2011年初夏、退社を決めイギリスに向かいました。
ロンドン留学。ドキュメンタリー写真
2011年からロンドン芸術大学に留学し、調査法、撮影法、写真ストーリーの編集法などを学びました。大学で写真とリサーチを学ぶ意義は、やはりしっかりとしたリサーチに基づき写真で表現していく方法論です。

留学中は、できるだけフィールドから学ぼうと思い、イギリスだけではなく、インド、スリランカにも長期滞在し写真ストーリーの制作をしました。
修了プロジェクトのテーマは、スリランカに約2ヶ月滞在し制作したセイロンコーヒーの復活プロジェクトです。ソーシャル・ネットワークで知り、参画を認めてもらい共にメンバーとして働き関係性を深めながら、物語を集め表現していきました。
写真ストーリーを作り上げて行くのと同時に、写真の活用についても模索していました。私は、表現するだけではなく、それを見た人も巻き込こんで意見を交換したり、アイデアを共に生み出すことに関心があったのです。
たとえば「コーヒーを嫌いな人は95%」というデータ単体より、苦味に顔を歪める顔を何人も見たときどれくらい普及への敷居が高いか実感することができるはずです。バナナとエスプレッソを組み合わせた甘さと苦さを組み合わせた商品は、そんな気付きから発想されました。

また、写真ストーリーは外部への物語を伝えてくれるだけではなく、農村部と都市部と離れて働くプロジェクトメンバー自身にも自分の仕事の前後関係を見て知ることでモチベーションをあげるメディアにもなりえます。


新しい船出
2014年に留学を終えたとき、これからは感性・表現と論理・分析を駆使した仕事をしていこうと決めました。それを推進していくため、写真家・ビジュアルリサーチャーの鬼頭とpear LLC.(ペア合同会社)を設立し、主に顧客や生活者の体験デザインにつなげていくためのリサーチや制作を中心に東京・神奈川を拠点に活動をしています。
長文にもかかわらず最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました。

その他の参考リンク:Shintaro Works